No.16
電波のはなし その3~周波数で変わる電波の特徴~
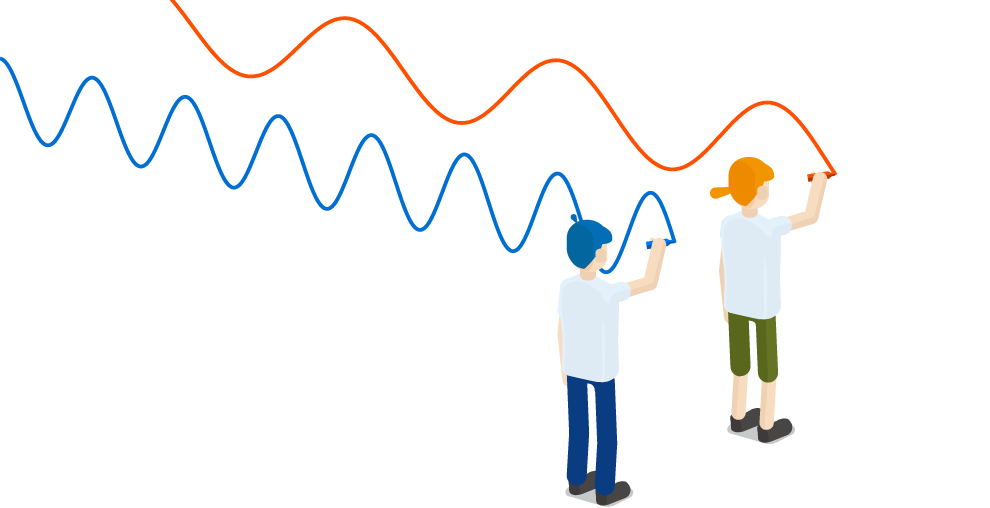
前回の記事「電波のはなし その2~「電波」は電磁波のひとつ~」では、電磁波が周波数によって分類されることをご紹介しました。日本で「電波」として利用されている周波数は3kHz(3000Hz)から3THz(3兆Hz)までの範囲です。当然ながら、3000Hzと3兆Hzとでは特徴が大きく異なります。そのため、電波は9つの「バンド」に分けられ、それぞれの用途に応じて割り当てられています。電波は国際的に利用される資源でもあるため、共通のルールも定められています。
今回は電波の特徴を知るうえで重要な「波長」と、周波数によって変わる電波の特徴について解説します。
※読み方 … kHz:キロヘルツ、MHz:メガヘルツ、GHz:ギガヘルツ、THz:テラヘルツ
電波の特徴を表す単位は「周波数」だけじゃない!
「波長」も重要!
前記事で、“決まった時間に波が繰り返される回数を「周波数」と呼び、1秒間に繰り返される波の回数を「Hz(ヘルツ)」という単位で表す” と説明しました。ただし、電波の特徴を表す単位は「周波数」だけではありません。電波には「波長」があり、これはアンテナの長さと密接に関係しています。
 4Hzと2Hzの波長を比較
4Hzと2Hzの波長を比較
上の図のように、波が1回振動する間に進む距離を「波長」と言います。
たとえば、4Hzと2Hzで比べた場合、1秒間に4回振動する「4Hzの波」よりも、2回しか振動しない「2Hzの波」のほうが波長は長くなります。
このように周波数が高いほど波長は短く、周波数が低いほど波長は長くなります。
では、波長を計算してみましょう。
計算方法は、「電波が1秒間に進む距離(単位:m)」を「波が1秒間に振動する回数」で割るだけです。電波の進む速さは周波数によって変わることはなく、光の速さと同じで約30万km/秒です。(ここで電波と光が仲間であるということが実感できますね)
この「30万km」の単位をmに変換すると「300,000,000m」になります。
しかし、300,000,000m/周波数(単位:Hz)では計算がしづらいため、計算式の周波数をMHz(1MHz=1,000,000 Hz)として、光の速さを300と置き換え、300/周波数(単位:MHz)とすることで計算がとても簡単になります。
つまり、電波の波長を求める計算式は下記のようになります。

たとえば、150MHzの電波の波長は2mとなります。
 150MHz、8Hz、4Hz、2Hzの電波の波長
150MHz、8Hz、4Hz、2Hzの電波の波長
※8Hz、4Hz、2Hzという電波は実在しませんがイメージとして描いています。
電波は周波数(と波長)によってアンテナの長さが変わる!
電磁波が周波数によって「電波」や「光」などに分類されるように、電波も周波数の違いによって伝わり方やアンテナの長さ、利用方法などの特徴が変わります。
周波数が低く、波長が長い場合
地面に沿って進みやすく、障害物の後ろへ回り込みやすくなります。このため、山やビルの陰でも受信しやすく、また遠くまで伝わりやすくなります。一方で、低い周波数の電波には「電波に乗せられる情報の量が小さい」「アンテナが長い(大きい)」という性質を持つようになります。たとえば、AMラジオ放送(531~1602kHz)で使用される電波では、送信アンテナはとても大きく、高さ百メートルを超える鉄塔が使われています。周波数が高く、波長が短い場合
直進する性質が強まり、光に近い特徴を持つようになります。このため、ビルや山などの陰では受信しにくくなり、また伝わる範囲が狭くなってきます。しかし、高い周波数の電波は「電波に乗せられる情報の量が大きい」「アンテナが短い(小さい)」という性質を持つようになります。たとえば、皆さんが使っているスマートフォンは高い周波数の電波(700MHz~28GHz)を使っていますが、そのアンテナの長さはわずか数センチメートルです(アンテナはスマートフォンの内部に組み込まれています)。
周波数により変わる電波の特徴
次回は電波の伝わり方
今回は「周波数」と「波長」についてお話ししました。
次回は、どのように電波が伝わっていくのか?について解説します。