No.20
緊急時、まずどうする?災害時の連絡ワザ集

たいていの災害はいつ起こるか分かりません。スマホの電波が圏外?バッテリー切れ?!…誰ともつながらない、安否が届かない――そんな不安を事前準備で解消しませんか?
今回は災害時の連絡手段についてまとめました。
緊急通報編
救助・救急は電話で「119番」
救助や救急の要請は119番に電話してください。電話がつながると、場所(住所または目印になる建物など)、状況、通報者の氏名、電話番号などを聞かれます。落ち着いて正確に伝えることで、より的確な応急処置やスムーズな救助・搬送ができます。なお、通報するときは自らの安全を確保したうえで行ってください。

携帯電話がつながらない!そんなときは公衆電話
災害時に多くの人たちが一斉に連絡を取り合おうとして電話回線が混雑し、緊急性のある通報が届かない…そんなことを防ぐため、私たちが普段使用しているような一般の電話(携帯電話だけでなく固定電話も含む)は通信制限される可能性があります。また、スマホや携帯電話のバッテリーはできるだけ温存しておきたいですね。そんな時に、近くにあれば頼りにしたいのが公衆電話です。
災害時、公衆電話は「災害時優先電話」として通信規制の対象外となり、優先的に使用できます(つながることが保証されているわけではありません)。また、公衆電話は電話回線を通じて電力を供給されているため、ケーブルに損傷が無ければ停電時でも電話ができます(一部の公衆電話を除く)。
公衆電話はデジタルとアナログの2種類があります。どちらも緊急通報する際の通話料金は無料で、硬貨やテレホンカードは必要ありませんが、操作方法が少々異なります。
- デジタル公衆電話の場合:受話器を上げる→「119」を押す
- アナログ公衆電話の場合:受話器を上げる→緊急通報ボタンを押す→「119」を押す
公衆電話について詳しくはこちら→総務省|公衆電話の使い方と使用方法
公衆電話の1台当たりの通信回数は減少傾向にあることから、需要が減っていることがうかがえます。災害時の有用性を考慮して今後も一定数は確保されるようですが、年々設置台数が削減されているので、生活範囲に設置された公衆電話の位置をチェックしておくと良いでしょう。
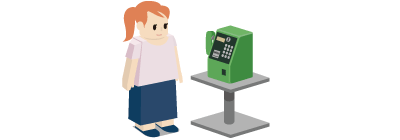
安否確認編
安否確認、どうやって連絡すればいい?
あなたが災害にあったとき、またはあなたの大切な人が災害にあってしまったとき、誰しもまず気になるのがその人の安否です。災害時はたくさんの人たちが一斉に連絡を取り合おうとしてインターネットや電話の回線が混雑することもあれば、通信設備が被害を受けるなどして、つながりにくくなることもあります。そのような状況で優先したいのは、人命にかかわる緊急連絡です。では、安否確認はどうすればいいのでしょうか?
あなたに合う安否確認の手段はどれ?
相手によっては連絡を受け取れる手段が異なる可能性もあります。例えば、インターネットが使えない人、公衆電話が設置されていない場所にいる人など、条件を考慮して連絡を取り合いたい人と事前に手段を考えておくと良いですね。用意していた手段が使えるとは限らないため、いくつも考えておくと安心です。
1.災害用伝言サービス
災害用伝言サービスとは、大規模な災害発生時に被災地への通信が増加し、携帯電話やインターネットがつながりにくくなると提供されるサービスです。音声の録音・再生や、テキストメッセージの登録・閲覧などができます。新しい伝言が登録されるとメールで通知してくれる機能もあります。利用には自分の電話番号や、安否を知りたい相手の電話番号が必要です。相手の電話番号は覚えておくかメモして持ち歩くと、携帯電話が使えない状況でも安心です。どのサービスも体験利用日が設けられています。
※サービスの利用料金は無料ですが、通信料金は各事業者へ確認ください。
電話を使う「災害用伝言ダイヤル(171)」
NTTコミュニケーションズが提供している「災害用伝言ダイヤル(171)」は、電話(加入電話、公衆電話、携帯電話・PHSなど)を使って録音・再生ができます。操作は171をダイヤルした後にガイダンスに従うだけです。録音時間は1伝言あたり30秒以内です。伝えるべきことを30秒にまとめるのは意外に難しいため、ぜひ体験利用日に試してみてください。「災害用伝言板(web171)」に登録されたメッセージを音声に変換して聞くこともできます。
インターネットを使う 携帯キャリアごとの「災害用伝言板」
各携帯キャリアが提供している災害用伝言板は、携帯電話・PHSでインターネットを利用し、テキストでの安否確認ができます。メッセージの登録は契約キャリアのサービスのみ可能ですが、メッセージの閲覧は他携帯キャリアの携帯電話・PHSの他、パソコンからも可能です。古いOSには対応していないこともあるため、OSバージョンの確認をしておく他、体験利用日に使用感を試しておくといいですね。
インターネットを使う 誰でも使える「災害用伝言板(web171)」
NTTコミュニケーションズが提供している災害用伝言板(web171)はインターネットブラウザを利用するため、契約キャリアに関係なく携帯電話・PHS・パソコン・タブレットからメッセージを登録・閲覧できます。災害用伝言ダイヤル(171)で登録された音声を聞くこともできます。
各携帯キャリアの災害用伝言板と災害用伝言板(web171)は連携しています。どの災害用伝言板から登録されたメッセージでも、全ての災害用伝言板から検索することができます。
災害用伝言サービスについて詳しくはこちら→総務省|災害用伝言サービス

2.SNS
SNSを使い慣れた方なら迷うことなく操作ができ、テキストメッセージの他、写真、音声、動画もリアルタイムで共有可能です。親しい人とのコミュニティがあれば、その人たちへ一斉に周知することができます。また、専用の安否確認機能が搭載されているものもあります。しかし、投稿や広告動画、画像などをたくさん読み込むタイプのものはバッテリーの消費が早い可能性があるためご注意ください。
LINEの安否確認機能
LINEの場合、家族や親しい人が集まったグループなど、送信先が1つ2つであればいつも通りのメッセージ送信で問題ないかもしれません。連絡したい相手がグループでまとまっていない場合は、「LINE安否確認」を利用してみてください。
大規模な災害が起こった際、ホーム画面にLINE安否確認の赤いバナーが表示されます。タップすると安否情報の入力と公開ができます。「友だち」が公開した情報は、「友だちリスト」にある「安否確認」から確認することができます。
体験版が利用できる日を公式サイトやSNSでチェックして、実際に使ってみてはいかがでしょうか。
Facebookの安否確認機能
Facebookには、つながっている人と安否確認ができる「災害時情報センター」という機能があります。2011年の東日本大震災をきっかけに開発した「災害用伝言板」を改良して現在の形に至ったそうです。
被災地にいると判断された利用者へ、Facebookから安否確認を促す通知が届きます。通知から災害時情報センターの画面を開き、安否状況を入力して報告すれば、つながっている人にのみ通知が送られます。つながっている人が報告した安否状況も災害時情報センターで確認できます。
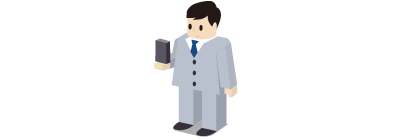
3.待ち合わせ
電話もインターネットも使えない!そんなときのために、待ち合わせ場所を決めておきましょう。待ち合わせ相手とすれ違わないためのポイントは次の3つ。
- 集合場所…【「学校」の「○○の前」】など、詳細に決める
- 集合時刻…【10:00と15:00】など、明確な時刻を指定
- 待ち時間…【15分間】【20分間】など、明確に区切る
待ち合わせ場所はハザードマップなども参考にして決めると良いでしょう。集合時刻や待ち時間は、気温が厳しい季節を考慮するといいかもしれません。悪天候の場合も想定して、安全のため大雨や台風の時は行かないように、など決めておくと良いですね。
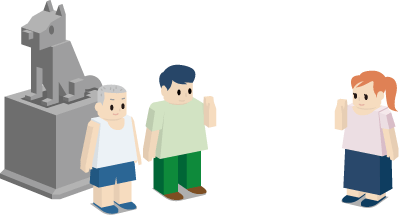
4.アマチュア無線
東日本大震災では、アマチュア無線局が安否情報などを発信して活躍したそうです。アマチュア無線は電話やインターネットなどの通信施設は関係なく、電源さえ確保できれば使用できます。
出典:総務省|アマチュア局による非常通信の考え方
免許や設備などの関係で使える方は限られ、発信時に受け取る相手がいなければいけませんが、一つの手段として考えておくと良いかもしれません。
詳しくは→総務省|アマチュア局による非常通信の考え方
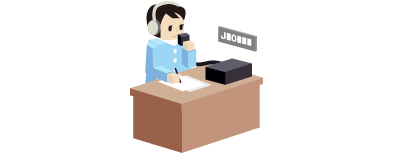
もしもの時に備えて
最後に、もしもの時に備えるポイントです。
- 災害時の通信事情や代替手段を知っておく
- 災害時に連絡を取り合いたい人と、連絡方法を事前に相談して決めておく
- 連絡方法は複数用意しておく
- 使い慣れていないツールは体験利用してみる
- 防災グッズに予備のバッテリーを入れておく、または非常用電源を準備しておく
- 公衆電話を使うときのために10円硬貨と電話番号のメモを持ち歩く
9月は防災月間として、さまざまな防災ツールが体験利用できる可能性があります。この機会に試して、災害に備えてみませんか。
